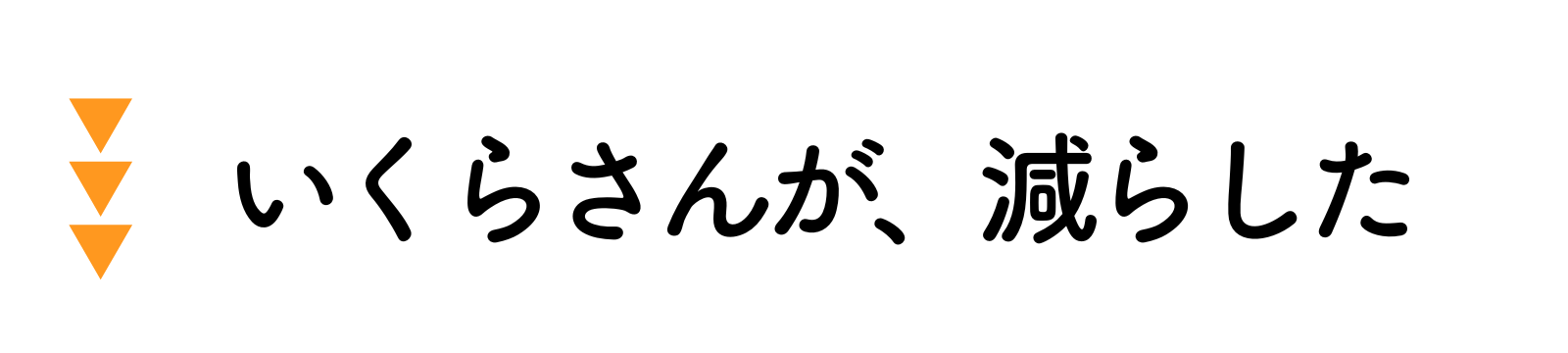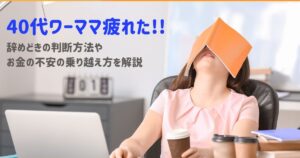- 時短勤務が終わった後、どうすればいいのか不安
- フルタイム復帰したら、仕事と家庭の両立を考えただけで憂うつ…。
- 転職するにしても、時短勤務OKの会社は見つかるの?
時短勤務が終わると、仕事量の増加や家計の負担、育児との両立といった課題が一気に押し寄せますよね。
フルタイムに戻るか、転職するか、退職して無職もアリか…。
後悔しない選択をするためには、しっかりと準備をすることが大切です。
私は正社員歴20年、ワーママ歴8年の元会社員です。
会社員ワーママ中は、時短勤務5年・フルタイム勤務3年を経験しました。
現在は在宅フリーランスの金融系WEBライターとして働いています。
FP2級の資格も持ち、家計管理や働き方の選択肢について情報を発信しています。
本記事では、時短勤務終了後に待ち受けるリアルな課題と、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを詳しく解説します。
さらに、時短勤務OKの転職先を見つける方法や、仕事と育児を両立するための工夫もご紹介します。
読めば、あなたに合った働き方が見えてくるはず。
「時短が終わったらどうする?」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
「疲れたワーママが正社員として働き続けるための対策」をメインに書いた別記事もあるので、気になる方はあわせてチェックしてください。
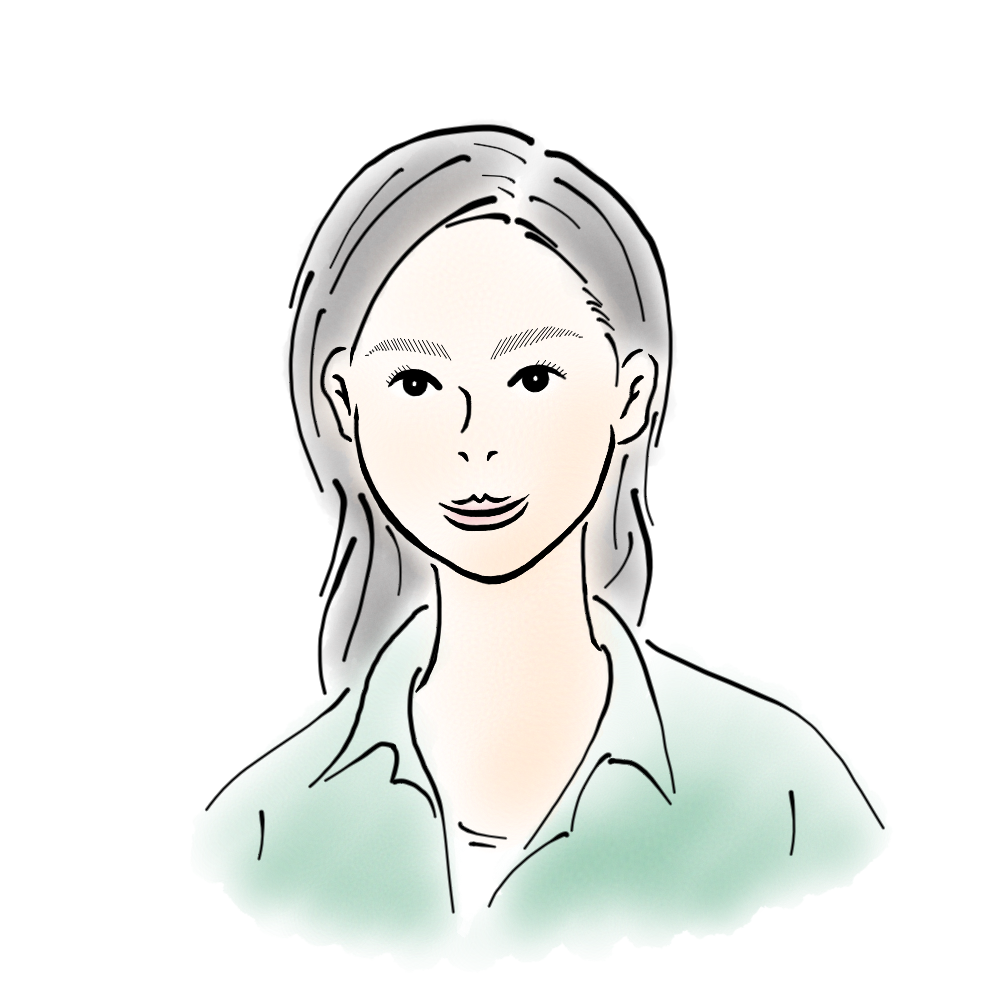
いくら
- 在宅フルタイムの金融系Webライター
- FP2級
- 会社員経験20年
(内ワーママ歴8年) - 子は11歳
- 会社を辞めたいと思いながら長年働き続け
2023年3月にやっと退職
時短勤務の基礎知識
時短勤務を利用する際に押さえておくべきポイントは、次の3つです。
- 時短勤務の適用条件と法律上のルール
- 時短勤務が認められる期間と企業の義務
- 企業による対応の違いと実際の運用状況
順番に説明します。
時短勤務の適用条件と法律上のルール
時短勤務の適用条件は、育児・介護休業法に基づき、3歳未満の子どもを育てる労働者が対象となります。
企業は、時短勤務を希望する従業員に対し、1日6時間の短縮勤務を認める義務があります。
ただし、一部の業種(雇用期間1年未満の労働者や特定の職種)では、適用外となるケースもあるため、自社の就業規則を確認することが重要です。
時短勤務が認められる期間と企業の義務
法律では、時短勤務が認められるのは「子どもが3歳になるまで」と定められています。
しかし、企業の制度によっては、小学校入学前までや、小学校6年生まで時短勤務を継続できる場合もあります。
また、企業には、時短勤務を希望する従業員の不利益にならないよう配慮する義務があります。
例えば、給与の減額ルールや昇進への影響について、明確な基準を設けている企業も増えています。
企業による対応の違いと実際の運用状況
時短勤務の運用状況は、企業によって大きく異なります。
大企業では制度が整っているケースが多い一方で、中小企業では人手不足を理由に、時短勤務を認めにくい場合もあります。
私を含めた友人・知人の例ですが、実際に時短勤務を経験した人の中には、以下のような声もあります。
- 「仕事量は変わらないまま勤務時間だけ短縮され、毎日時間に追われた」
- 「6時間で仕事を終わらせるために、勤務時間中は常に張り詰めていて精神的に疲れた」
- 「周囲に気を遣いながらの勤務で、肩身の狭い思いをした」
時短勤務をスムーズに利用するためには、会社の制度だけでなく、職場の雰囲気や上司・同僚の理解度も重要なポイントとなります。
事前に上司と話し合い、業務調整の相談をしておくことで、無理なく時短勤務を活用しやすくなるでしょう。
時短勤務が終わった後の課題
時短勤務が終わると、フルタイムに戻るか、新しい働き方を選ぶかの決断を迫られます。
時短勤務中と同じ感覚でいると、思わぬ負担に直面することもあるため、事前に準備しておくことが大切です。
時短勤務終了後に直面する主な課題として、次の3つが挙げられます。
- 仕事量・残業が増える
- 家庭にしわ寄せが出る
- 出費が増える
順番に説明します。
仕事量・残業が増える
時短勤務が終わると、労働時間がフルタイムに戻るため、業務量の増加は避けられません。
それまで時短勤務でこなしていた業務に加え、新しい仕事を割り振られる可能性が高いでしょう。
また、フルタイム勤務になることで残業を求められるケースもあり、ワークライフバランスが崩れやすくなります。
特に、時短勤務中に「他の人に仕事を頼むのが申し訳ない」と感じていた人ほど、フルタイム復帰後に責任感を強く感じ、無理をしてしまいがちです。
結果として、仕事に追われ、育児や家庭とのバランスが取りにくくなることも。
家庭にしわ寄せが出る
フルタイム復帰すると、帰宅時間が遅くなり、家事や育児にかけられる時間が減ります。
夕飯の支度や子どものお迎え、お風呂、寝かしつけまでの流れが、仕事帰りの短い時間に詰め込まれるため、親の負担はもちろん、子どもにも影響が出ることがあります。
また、家事分担がうまくいっていない場合は、「夫のほうが帰りが遅いから」といって家事をすべて自分が背負い込んでしまうケースもあります。
その結果、身体的・精神的な負担が増え、夫婦関係にも影響を及ぼすことがあるため、事前に家族と話し合い、協力体制を整えておくことが大切です。
出費が増える
フルタイム復帰後、出費が増えることも避けられません。
具体的には以下のような支出が増える傾向にあります。
- 延長保育料・学童保育費(時短中より長時間預けるため)
- タクシー代(保育園や習い事の送迎で急ぐ必要がある場合)
- 外食・中食費(仕事帰りに夕飯を作る余裕がない)
- 家事代行・シッター費用(家事・育児の負担を減らすため)
これらの出費を抑えるためには、事前の計画が必要です。 例えば、
- 週末にまとめて作り置きをして平日の外食を減らす
- 夫婦で送り迎えを分担してタクシー代を節約する
- 固定費(通信費・保険など)を見直して家計に余裕を持たせる
といった工夫を取り入れることで、支出をコントロールできます。
 いくら
いくら一人で節約の戦略を立てるのが難しい場合は、無料FP相談の活用もおすすめです。
時短勤務が終わった後のキャリア選択肢
時短勤務が終わると、フルタイム復帰だけでなく、転職や別の働き方を考える人も多いと思います。
私もそうで、同じ職場のまま、フルタイムをこなす自信はゼロでした。
時短勤務終了後のキャリアの選択肢として、主に以下の3つがあります。
- フルタイム復帰
- 時短勤務が可能な会社へ転職
- パート・フリーランス
選択肢ごとのメリット・デメリットを理解し、今後の働き方を見つめ直してみましょう。
順番に説明します。
フルタイム復帰
フルタイム復帰を選ぶと、収入が増え、キャリアを継続できるという大きなメリットがあります。
また、時短勤務中に感じていた「周囲への気遣い」から解放されることで、肩身の狭さを感じずに働けるのも利点の一つです。
一方で、勤務時間が増えることで家事や育児の負担が大きくなり、生活スタイルの変化に適応する必要があります。
フルタイム復帰後にスムーズに仕事と家庭を両立するためには、家族との分担や、時短家電・外部サービスの活用を事前に計画しておくことが重要です。
時短勤務が可能な会社へ転職
「フルタイム勤務は難しいけれど、仕事は続けたい」という場合、時短勤務が可能な会社への転職という選択肢もあります。
時短勤務を受け入れている企業は、IT業界や事務職、カスタマーサポートなどに多い傾向があります。
転職を考える際には、求人サイトの検索条件で「時短勤務可」「育児支援あり」などを設定し、企業の実績をリサーチすることが重要です。
また、履歴書や面接では、「時短勤務でどのように成果を出せるか」を明確に伝えることがポイントになります。
例えば、「短時間で効率的に業務を進められること」「これまでの実績を活かして即戦力として貢献できること」などを強調すると、採用される確率が高まるようです。
転職エージェントの1つに、時短正社員に特化した「リアルミーキャリア」という会社があるので
- まずは登録
- どういう仕事が紹介されるのか?を確認
がおすすめです。
登録するのが遅くなると、年齢が理由で紹介件数が少なくなる可能性もあります。
だから今すぐ無料登録だけでもして、自分の市場価値を確かめてみることをおすすめします。
\ 1分で完了 /
パート・フリーランス
「フルタイムも時短勤務も難しい」と感じる場合は、パートやフリーランスといった柔軟な働き方を選ぶのも一つの方法です。
- パート:勤務時間の融通がききやすいが、収入が限られる
- フリーランス:働く時間や場所の自由度が高いが、収入が安定しにくい
フリーランスの場合は、在宅でできるWebライターやデザイナー、オンライン秘書などの仕事が、家庭との両立に向いています。
パートを選ぶ場合も、「扶養内で働くのか、それともしっかり収入を得るのか」を事前に考えておくことが大切です。
時短勤務OKの会社への転職成功パターン
転職を考えるなら、時短勤務OKの企業を選び、履歴書や面接での伝え方を工夫することが成功のポイントです。
企業ごとの対応や評価基準を知り、効率的に転職活動を進めましょう。
時短勤務OKの転職成功パターンとして、以下の2つが挙げられます。
- 履歴書・面接での時短希望の伝え方を工夫する
- 時短勤務でも評価される働き方と実績をアピールする
順番に説明します。
履歴書・面接での時短希望の伝え方を工夫する
時短勤務希望を伝える際は、企業側が不安を感じないように「なぜ時短勤務が必要なのか」「短時間でどのように貢献できるのか」を明確にすることが重要です。
例:「現在、育児と仕事の両立を図るため、1日6時間勤務を希望しております。
限られた時間の中で最大限の成果を出し、業務に貢献できるよう努めます。」
例:「勤務時間は短縮されますが、業務効率化を意識し、限られた時間内で成果を最大化できるよう努めます。」
また、時短勤務を希望することで不採用にならないように、時短勤務後のキャリアプランについても話せるとより好印象です。
時短勤務でも評価される働き方と実績をアピールする
時短勤務であっても、企業にとって「成果を出せる人材」と認識されることが重要です。企業側が「時短勤務だから戦力にならないのでは?」と懸念しないように、過去の実績やスキルをアピールしましょう。
例えば、以下のような工夫が評価されやすいポイントになります。
例:「これまでの業務では、タスク管理を徹底し、残業なしでも納期を守りながら業務を遂行してきました。」
例:「6時間勤務の中で、業務の効率化を進め、通常8時間勤務の社員と同等のパフォーマンスを発揮しました。」
「同じ会社の時短勤務者の働き方を研究し、成果を上げている人の業務フローを取り入れました。」
このように、「時間が短くても、フルタイムと同じくらいの成果を出せる」という姿勢を見せることで、採用側の不安を軽減できます。
時短勤務が終わった後の仕事と育児の両立法
フルタイム復帰後、仕事と育児の両立に悩む方は多いでしょう。**「仕事が終わらない」「家事に追われる」「育児の時間が取れない」**など、両立の壁に直面するケースも少なくありません。
しかし、すべてを完璧にこなそうとすると、心も体も疲れ切ってしまいます。大切なのは、家族の協力を得ながら、家事・育児の負担を減らし、無理なく続けられる仕組みを作ることです。
仕事と育児を両立するためのポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- フルタイム復帰後の出費増と節約のポイントを知る
- 家事・育児の分担と効率化のコツを取り入れる
- 外部サービス(家事代行・シッター)を活用する
順番に説明します。
フルタイム復帰後の出費増と節約のポイント
フルタイムに復帰すると、家計の負担が増えることがあります。特に、以下のような費用が増えるケースが多いです。
- 延長保育料・学童保育費(預け時間が長くなるため)
- タクシー代(急な送迎や通勤時間短縮のため)
- 外食・中食費(料理をする時間が取れない日が増える)
- 家事代行・シッター費用(家事や育児の負担を減らすため)
これらの出費を抑えるためには、家計の見直しや生活スタイルの工夫が必要です。
例えば、
- 食材の作り置きや宅配サービスを活用し、外食費を減らす
- 夫婦で送迎を分担し、タクシー代を抑える
- 通信費・保険などの固定費を見直して、家計に余裕を持たせる
など、できそうなものから少しずつでも取り入れることで、あまり無理なく節約できます。
家事・育児の分担と効率化のコツ
家事・育児の負担を減らすためには、役割を固定しすぎず、柔軟に分担することが大切です。
例えば、
- 「パートナーと家事・育児のシフト制を導入する」
- 「できることをリスト化し、協力しやすい環境を作る」
といった工夫が有効です。
また、渡しの場合は「日用品・食材の買い出しはネット一択」にすることで、買い物の時間と負担感を削減できました。
さらに、食洗機やロボット掃除機などの時短家電を活用することで、家事の負担を大幅に軽減できます。
外部サービス(家事代行・シッター)を活用する
「家事や育児をすべて自分でこなすのは大変」と感じる場合は、外部サービスを利用するのも一つの選択肢です。
活用できるサービス例:
- 家事代行サービス(掃除・料理などを依頼できる)
- ベビーシッター(保育園のお迎えや、一時預かりなど)
- 食材宅配サービス(調理済みのミールキットや、カット野菜の宅配)
サービスを利用する際は、コストや頻度を考えながら、必要な部分だけ取り入れるのがポイントです。
例えば、「週1回だけ家事代行を頼む」「忙しい日だけミールキットを活用する」といった工夫をすると、無理なく続けられます。
まとめ
時短勤務が終わった後、フルタイム復帰や転職、別の働き方を選ぶかどうかは、多くのワーママが悩むポイントです。
どの選択肢を選んでも、仕事量の増加や家計の負担、育児との両立といった課題に直面することになります。
だからこそ、事前に情報を集め、自分にとって無理のない働き方を考えておくことが大切です。
本記事では、時短勤務終了後に起こり得る課題や、選べるキャリアの選択肢、仕事と育児を両立するための工夫を紹介しました。
✔ フルタイム復帰は収入やキャリア面で有利だが、仕事量の増加や家事・育児の負担も大きくなる
✔ 時短勤務OKの会社へ転職するなら、業界・職種の選び方や面接でのアピールが重要
✔ フリーランスやパートなど、柔軟な働き方も選択肢に入る
✔ 仕事と育児を両立するためには、家事・育児の分担や外部サービスの活用が鍵
すべてを完璧にこなす必要はありません。
あなたにとって最適な選択肢を見つけ、仕事と家庭のバランスを整えていきましょう。